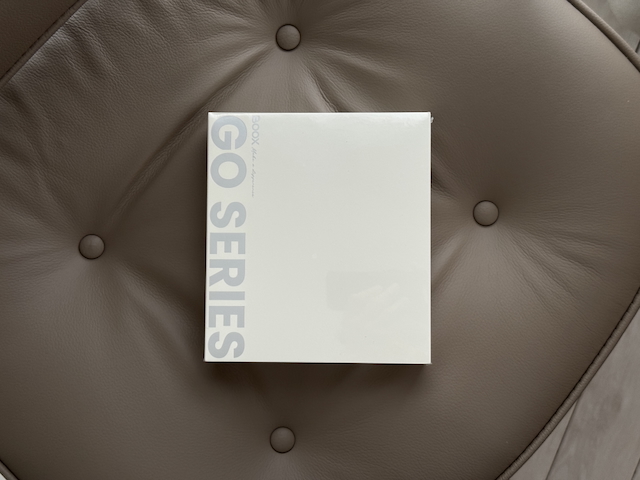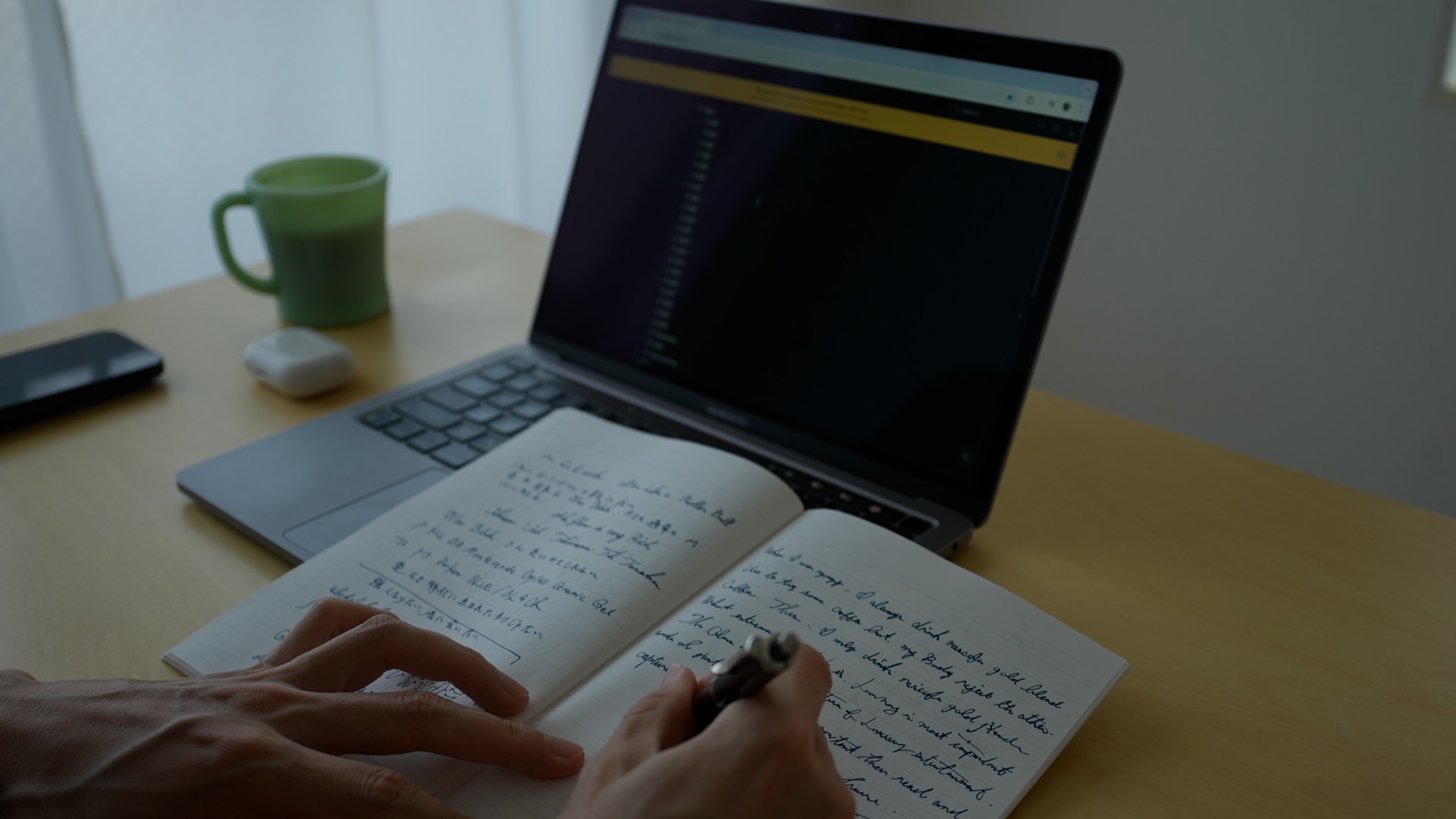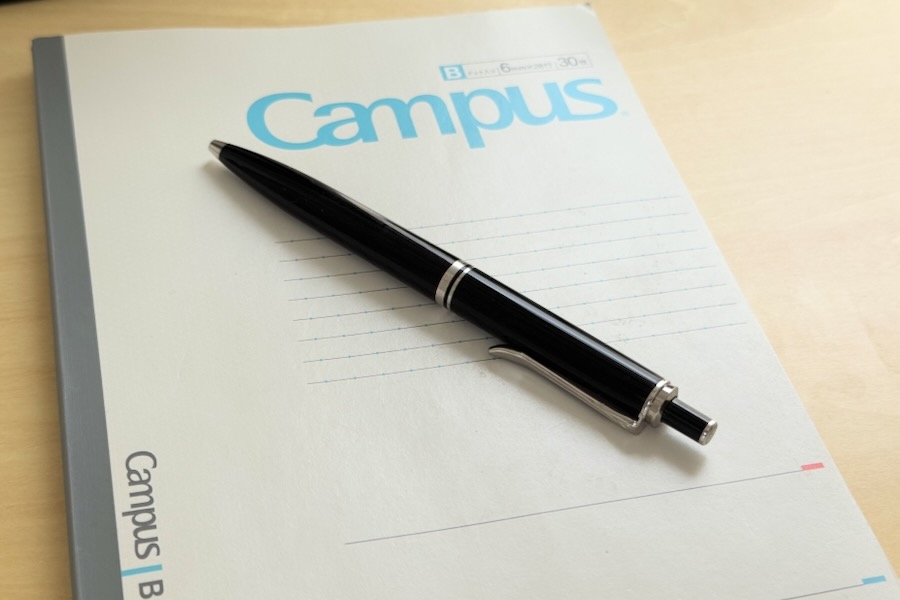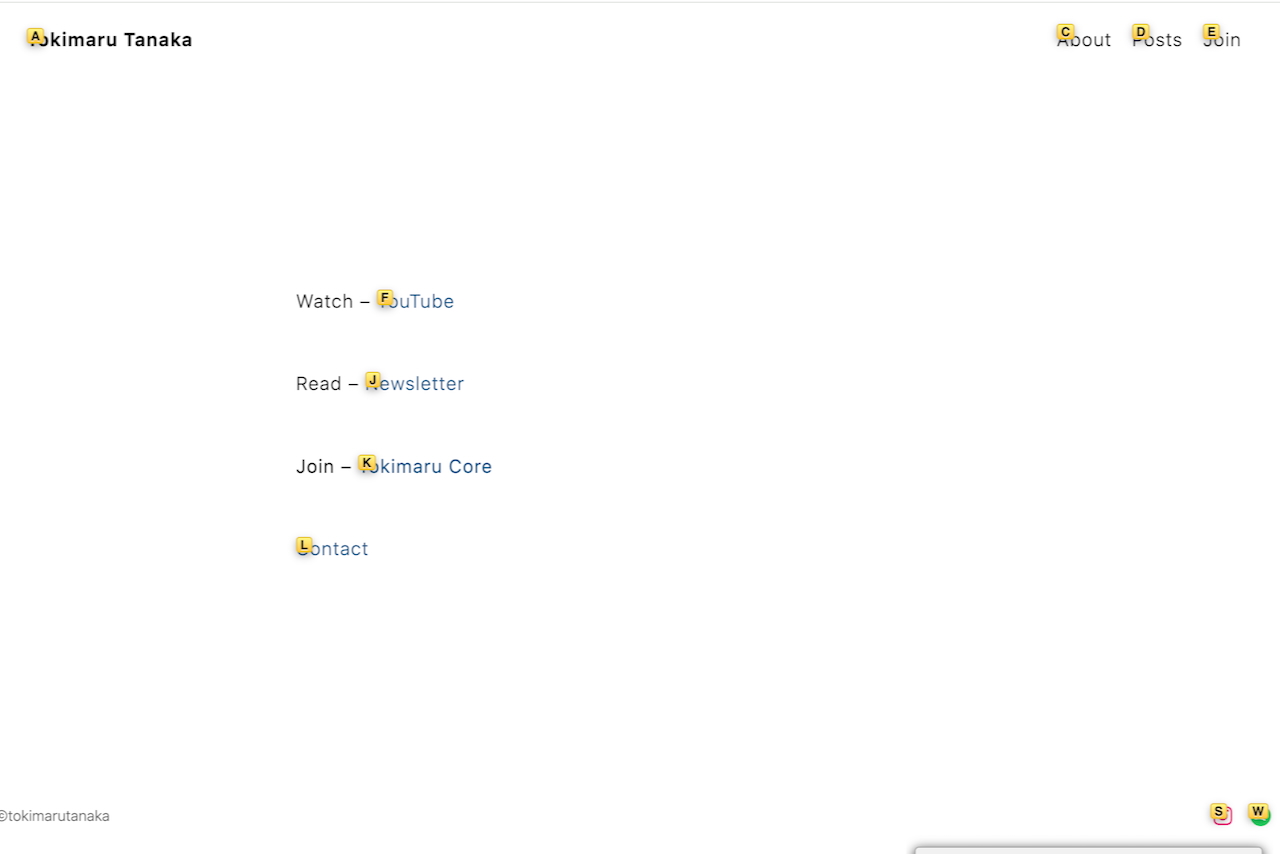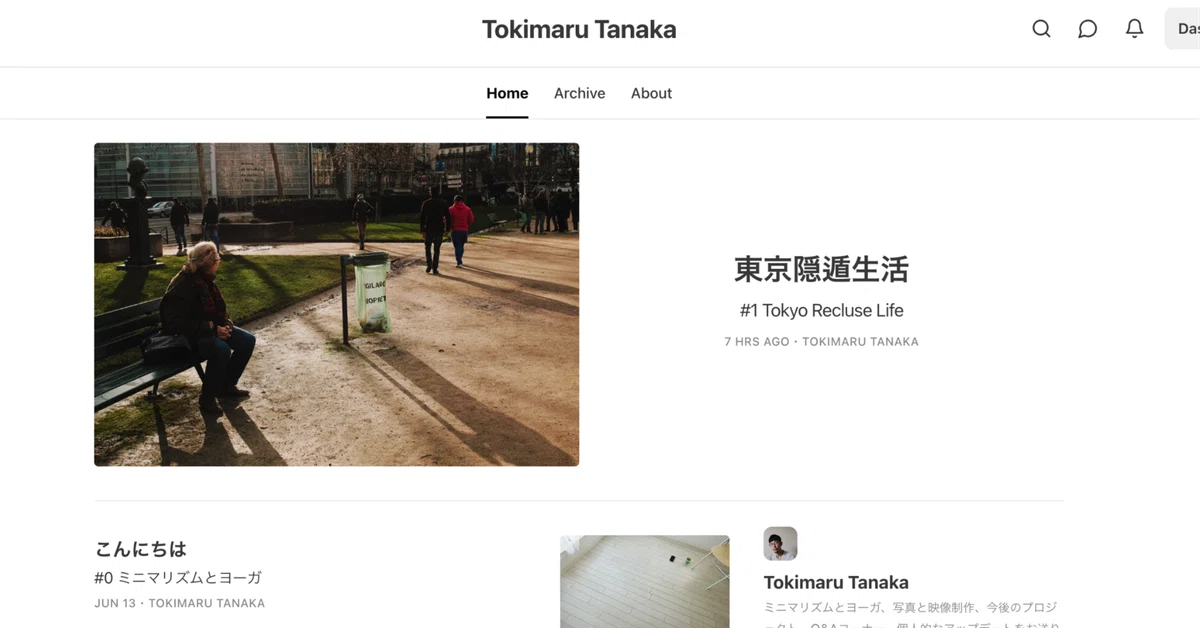ソロプレナーという言葉には、単なる働き方以上の思想が含まれている。
Solo(ひとり)とEntrepreneur(事業を起こす人)を掛け合わせた造語は、もともと米国や欧州のテック文脈で、個人開発者や小さなチームがプロダクトを作り、運用し、収益化まで担う姿を指して広まった。だが本質はコードを書く人だけに閉じていない。むしろ最近はAIの力によって、様々なかたちのソロプレナーが生まれていると感じる。重要なのは、複製可能な創作物を武器にして、事業を自分の手で設計し、意思決定の速度と生活の自由度を最大化するという点にある。
ソロプレナーの魅力を一言でまとめるなら、自分の時間を自分で決められることだ。会社員や、クライアントワーク中心のフリーランスは、どれだけ裁量があるように見えても、締め切りや稟議、会議、現場への移動、相手都合の調整に人生が侵食されやすい。
もちろんそれ自体が悪いわけではない。しかし、瞑想やヨガのように、長い時間軸で積み上げる営みを生活の中心に置きたい人にとって、誰かの時間に左右される構造は致命的になり得る。馬鹿げた話かもしれないが、アシュタンガヨガにどハマりした2023年、仕事などしてる暇はない、ずっとヨガだけをしていたいと本気で思っていた。
朝起きて、その日やることや優先順位を自分で決められるか。集中の波が来たら深く潜れるか。逆に、一切何もせずに整える時間を取れるか。ソロプレナーは、その主導権を自分の側に取り戻すための仕組みだ。自分の人生を取り戻すための行為という点では、ミニマリズムと同様であると言える。
圧倒的に自由である代わりに、引き受けなければならないことも多い。ソロプレナーは、0から1の立ち上げだけではなく、1になった物事を回し続ける運用まで全てを担う。事業や会社全体の設計、プロダクト設計、販売のための導線づくり、マーケティング、広報、顧客対応(CS)、改善。会社なら分業される工程が、基本的に自分に集約される。そういう意味ではジェネラリスト的性質の人が有利である。これは言い換えれば、何かの専門分野に特化したスキルを持っていなくても、ソロプレナーになれる可能性があるということだ。昨今はAIがその可能性を広げている。
ここで多くの人が誤解するのは、ひとりで稼ぐ=気楽というイメージだ。実際には、気楽かどうかは人による。自分で決めたい人にとっては快適で、決めることが負担な人にとっては過酷になる。だからソロプレナーを目指すべきだ、と主張したいわけではない。むしろ、向き不向きを明確にし、自分に合う仕組みを選ぶために、この働き方を言語化しておく価値がある。
面白いのは、ソロプレナーという言葉がコードを想起させる一方で、文章にも同じ構造があること。コードも文章も、テキストとして書かれ、編集され、複製可能で、蓄積され、場合によっては資産になる。コードはコンピューターのソフトウェアを動かし、文章は人間のソフトウェア(脳)に作用している。文章には読む人の意思決定、行動、価値観、習慣を変える力がある。つまり、執筆者もまた、別の意味での開発者になり得るのだ。
エディタで書き、改善し、公開し、フィードバックを得てアップデートする。この循環は、プロダクト開発のサイクルと驚くほど似ている。
ソロプレナーの核は、クライアントワークから距離を取り、自分の作品資産を積み上げることにある。