-
キャッシュレスとクレカ最適化 – ミニマルに最大効率を目指す(2025年春版)
ポイント優位なクレカを選ぶことは、今や常識になった。ミニマリズムと節約、財テクのようなものを掛け合わせると、キャッシュレス決済も所有するクレジットカード類も最小にして、ポイントは最大効率にするという思考を取れる。資産形成を加速させながらも、カードの枚数や管理コストは極力減らしたい。これまでのクレカヒストリーについては、こちらの記事で詳しく書いたが、最近は三井住友ゴールドNLをメインに使い、SBI証券のクレカ積立にも活用しながら、ほぼこの1枚で生活のすべてを回してきた。年100万円を使えば年会費が無料になり、1万ポイントが確実に得られる。(実質還元1.5%)PayPayにも紐づけて使えるため、支払領域を広げられ、これ1枚で完結していた。
だが2025年現在、いくつかの前提が変わり始めている。1つは、ゴールドNLは年100万円を超えて使っても、ボーナス還元ポイントは増えないため、実質的な還元率は低下していくということ。たとえば年間130万円を使ってもボーナス還元は1万ポイントのままなので、通常の0.5%還元を考慮すると還元率は1.27%となる。しかも、SBI証券でのクレカ積立分(月10万円)は、年100万円利用のカウント対象外である。それでも還元率が1%を超えるのは、多くのクレカの中では優秀である。しかし今年に入って、常時1.5%のカードが現れてきたのだ。
-
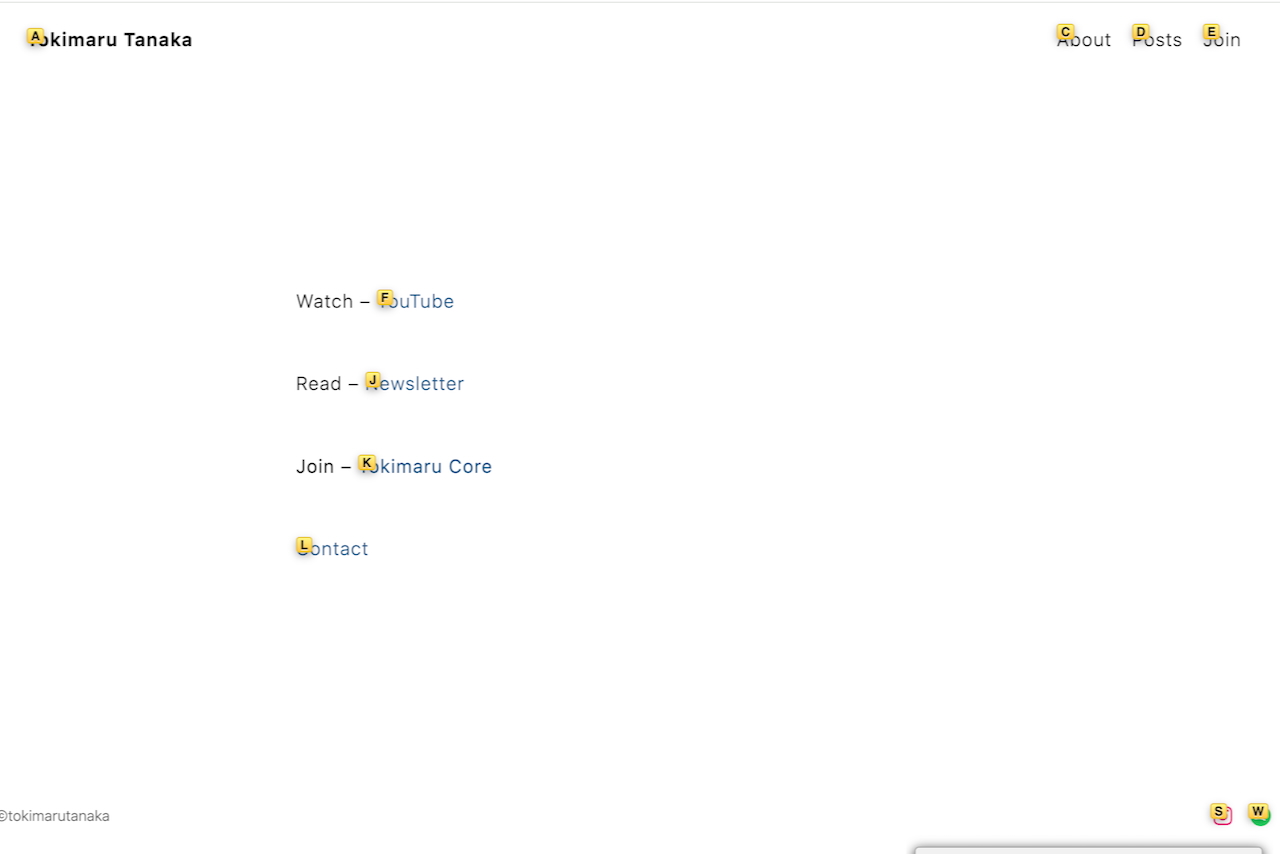
最小構成でのMac操作最適化
Macの最適化には終わりがない。ワードプレスやWorkflowy、書くツールが変わるたびに、使いたいショートカットキーやツールも変わり、いつも迷子になる。迷子になっても館内放送で「Tokimaru Tanakaさま〜」と誰も呼んでくれないので、迷路から抜け出すには新たな技術を自分で学び直すしかない。わかっているけど、いつもの癖が抜けない、同じ環境で同じツールを使いがち。メンバーシップをnoteからCoreに移してから、自分にとっては再びワードプレスで書くことの重要性が高まっているわけだが、その前にちょっとMac自体を最適化してみようと思った。
表現の質と量を高めるためには、思考と操作の距離を極限まで縮める必要がある。それはPC操作以外にも言える。マウス操作、ファイル検索、ウィンドウ切り替えといった小さな操作の遅延は、集中力と創造性の障害になる。そこで今回、Mac上のすべての作業をキーボードのみで完結させることを目的とした。
使用ツールと役割
-

MacBookひとつで生きるという究極のミニマリズム
MacBookが一台あれば、他にはもう何もいらない。そう思うようになったのは、ずいぶん前のことだ。
ミニマリストにとって、iPhoneが重要なアイテムであることに異論を唱える人はまずいないだろう。実際、iPhoneはそれ自体がミニマリズムの体現であり、一台であらゆることを済ませることができる。しかし、多用途性という観点で考えれば、MacBookはさらに広い世界を見せてくれるのではないだろうか。
僕が初めて買ったコンピューターはWindows 95が登場した頃の富士通の巨大なデスクトップだった。その頃のパソコンといえば、重くて場所をとるデスクトップが主流で、ノート型は性能が劣る割に値段が高い、ちょっとした贅沢品のような存在だった。実際、当時のラップトップは今とは比べ物にならないほど大きくて重かったから、持ち運びのメリットなどほとんどなかったのだ。
そんなイメージを一新したのが、ソニーのVAIOシリーズだった。薄くてスタイリッシュなデザインは、ノートパソコンの可能性を一気に広げ、小型化と軽量化の時代を切り開いた。
-

Extreme Minimalist Wardrobe 2025 S/S
毎年アップデートしているミニマリストワードローブ。 2025年は、より専属的な活動スタイルと、レイヤリング設計のみならず、素材の実験ベースでの最適化を模索し、後悔なく「最小の所有」を実現できるラインナップに到達しました。
この記事は「Tokimaru Core」のコアな皆さんに向けて、持ち物に関する全プロセス、素材スペック、選定の背景、レイヤリングの理論、そして最後に残った意味のある最小構成を記録するものです。動画版はYouTubeをご覧ください。
目次
- ミニマリズムの哲学と生活スタイル
- レイヤリング理論:都市と山の往復生活
- 最終ラインナップ:選ばれし衣類一覧
- アイテム個別分析:選定理由と素材評価
- 「着ない服がない」ことの安心感
- 今後のアップデート予測
- おわりに:65点で生きるという実験
-
2025/04/09
Substackの記事の一部をTokimaru Coreに移管しました。
-
エクストリームミニマリストの買い物リスト

最近の朝食の風景 私の最近の買い物リストをご紹介します。
12月に入り、朝食をパンからオートミールに戻しました。それに伴い、オートミールで補える栄養素を考慮してサプリメントを調整し、減らしました。その結果、体調が良くなり、朝食の時間がより楽しみになっています。
以前から「スーパーでの買い物リスト」を作成していることをお話ししてきましたが、ここでは私の最新(2024年12月の記事)の買い物リストを公開します。
